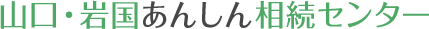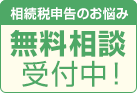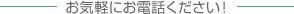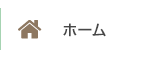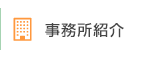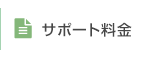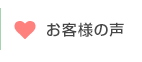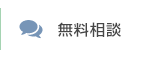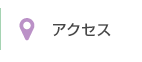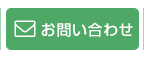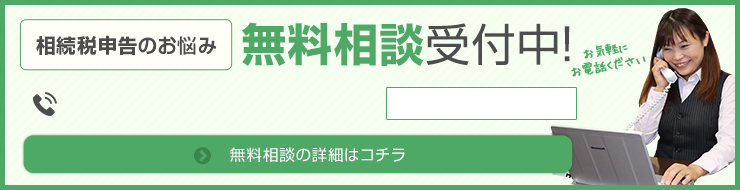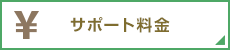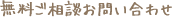No1「相続人」「法定相続人」の違い
相続を考えるときに必ず出てくるのが「相続人」という言葉。
相続税の世界では「相続人」のほかに「法定相続人」という言葉が出てきます。
「法定相続人」とは
法定相続人とは、相続が発生した際に、民法の定めるところに従い、財産を相続できる人のことを指します。
たとえば、つぎのケースの場合、、、

父が亡くなった場合、「法定相続人」は配偶者である母と子である長男、長女の3名です。
長男が相続放棄をした場合、相続の手続上 長男は「相続人」でなかったものとして取り扱います。
したがって、「相続人」は母と長女の2名となります。
つまり、『法定相続人』とは「相続人」のほかに「相続放棄したひと」も含まれることになります。
「法定相続人」と「相続人」の違いは民法で規定されるところの相続人が「法定相続人」であり、実際に相続をする人が「相続人」ということになります。
法定相続人の範囲は?
まず、亡くなった方の配偶者は、状況に関わらず必ず相続の権利を持ちます。これに続くのが、第1順位の相続人であり、これには故人の子が含まれます。子が既に亡くなっている、もしくはいない場合には、その子供たち、つまり孫がこの位置を継ぎます。孫もいない場合には、さらにその下の世代、ひ孫が相続人となります。
もし第1順位の相続人が一人もいない場合、次は第2順位の相続人が相続権を持ちます。第2順位には故人の父母が位置づけられ、父母が既に亡くなっている場合には、祖父母がその権利を受け継ぎます。
そして、第2順位の相続人もいない場合には、第3順位の相続人が遺産を受け継ぐ権利を持ちます。これには故人の兄弟姉妹が含まれ、兄弟姉妹がいない場合には、その子供たち、すなわち甥や姪が相続人となります。
相続人の順位は、上位の順位に該当する人がいない場合に限り、次の順位へと移行します。このようにして、故人の遺産は法律に則って適切に継承されていくのです。
法定相続人の確認方法
法定相続人を確定するためには、被相続人の家族関係を正確に把握する必要があります。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、家族構成や婚姻歴、子の有無などを確認します。
主な手順は以下の通りです:
-
戸籍謄本の収集
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。これにより、被相続人の婚姻歴や子供の有無、認知した子供などの情報を確認できます。
-
相続関係説明図の作成
- 収集した戸籍謄本を基に、被相続人と相続人の関係を図示した「相続関係説明図」を作成します。これにより、相続人の範囲や相続順位が一目で分かります。
-
法定相続情報一覧図の作成と利用
- 法務局の「法定相続情報証明制度」を利用し、法定相続情報一覧図を作成・取得します。これにより、相続手続きの際に何度も戸籍謄本を提出する手間を省くことができます。
以上の手順を踏むことで、法定相続人を正確に確定し、円滑な相続手続きを進めることが可能です。相続人の確認は、遺産分割協議や各種相続手続きの基礎となる重要な作業ですので、慎重に行いましょう。
相続税の基礎控除額を計算する際の計算式は
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
600万円にかける人数は相続放棄したひとも含める ということになります。
まとめ
相続手続きは複雑で、多くの専門知識が求められますが、法定相続人と相続人の違いを正しく理解することは、スムーズに進めるための第一歩です。特に相続税の計算や相続放棄が絡む場合、法律的な解釈を間違えると予想外のトラブルにつながることがあります。
そのため、専門家のアドバイスを受けることが大切です。当事務所では、相続に関する豊富な経験をもとに、個々の状況に合わせた最適なサポートを提供しております。相続についての疑問や不安がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。